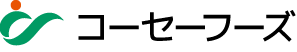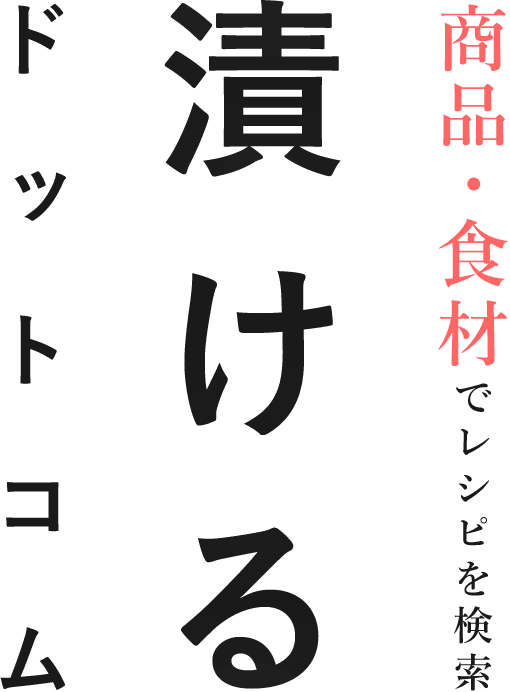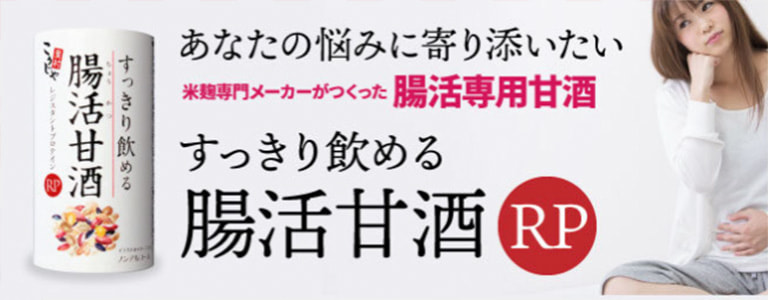お酢の豆知識
基礎知識
古代は健康飲料だった
一説には五千年の歴史を持つといわれているお酢。古代の人は薬効のある飲み物として引用していたそうです。かの有名なクレオパトラが美貌のために酢の中に真珠を溶かして飲んでいたという逸話もありますよね。
原料によって風味が変わる
調味料は化学薬品から作る合成酢、かんきつ類などの果実の酸味を利用して作る果汁酢、穀類などから醸造して作る醸造酢の3種類に大別されます。醸造酢の原料は米、酒粕、リンゴ、ブドウ、麦芽など。それぞれの原料の特徴による風味の違いを調理によって使い分けたいですね。
「ポンズ」は何語??
もともとはオランダ語で、かんきつ類の果汁を意味していました。現在は、レモンやスダチ、ユズなどのかんきつ類の果汁に酢を加えて作られます。
黒酢は赤血球をやわらかくする
酢を飲むと体がやわらかくなると言われますが実際実験したところ変化はなかったのですが、中年男女9人に毎日20mlの黒酢を2週間に続けた結果、全員の血液が流れやすくなったそうです(NHKためしてガッテンより)
黒酢は屋外で作られるため、酢酸以外のいろいろな成分が含まれているそうです。それらが赤血球をやわらかくする効果を生むらしいのです。
【黒酢とは】原料は普通のお酢と全く同じ米と利用するが、屋外の壺の中で熟成させるため、複雑な発酵がおき、色も黒く香りや味も濃厚なのが特徴。
南の人は酢を好む!?
国の酢の消費量は、沖縄を除き、南に行くほど増えています。暑い土地では、食欲増進効果や殺菌効果に役立つため好まれているようです。
酢の食欲増進作用(NHK ためしてガッテンより)
砂糖・塩・味噌・醤油・酢の5種類の調味料を舌にのせ、分泌される唾液の量を調べたところ
砂糖 ※※
塩 ※※※※
味噌 ※※※
醤油 ※※
酢 ※※※※※※※※※※※
圧倒的に酢が多いことがわかりました。つまり食用増進効果があるのです!!
さらに酢には苦味を抑え、甘味を強調する働きもあるそうです。食欲のない時は酢の物やマリネ、ピクルスを前菜にすると良いですね。
酢の防腐殺菌効果
魚を水洗いしただけの場合と酢で洗った場合の、1g当たりの細菌の数を比較したところ・・・
■水洗いだけ・・・9800個/g →1時間後・・・1300000個/g
■酢洗い・・・・・ 350個/g →1時間後・・・・ 2900個/g
酢には殺菌効果だけでなく、1時間後も殺菌を増やさない効果があるようです。
南の地方の郷土料理に酢がよく使われているのは昔の人の知恵なんですね。
玄米酢は高血圧を防ぐ!
高血圧
高血圧は遺伝、年齢、性別、食事、ストレス・・・など、さまざまな要因がかかわりあって起こりますが、直接的なことは実はよくわかっておりません。一般的には男性に早く現れ、年齢とともに患者数も多くなりますが、最近では20代の患者数が多くなり若年化が問題となっています。その他、肥満者に多い事や遺伝的・体質的なこともあったりと、他の病気との関連も深いので注意が必要でしょう。
塩分の摂り過ぎは大問題
塩分の摂り過ぎが高血圧に結びつく事は常識的なことですが、その理由を正確に言える人は少ないのではないかと思います。塩分を摂り過ぎると血液中に水分が集められ、血液量が増え、血圧が上がります。この状態が続く事が高血圧となります。高血圧は心臓や全循環系の肝臓に負担をかける為、他の病気を誘発する可能性も高いのです。そんなことから食事時の塩分を考える必要があります。
玄米酢をうまく使う
玄米酢が高血圧にいいと言う事は意外に知られていません。玄米酢は尿を促す作用があり、飲む事や食事に利用する事で一日の尿量を増やす事ができます。玄米酢の乳酸がナトリウムを吸収し、乳酸ナトリウムとして排泄され、またカリウムもナトリウムの排泄を促します。味付けの面でも、料理に玄米酢を使う事により、塩分を減らす事ができ、塩味を引き立てる働きも持っています。マヨネーズ、ドレッシングはまさにその考えを応用したものといえます。漬物にも酢漬け(ピクルス)がありますが、塩分を抑える機能食と言っていいのかも知れません。ただ、当たり前ですが、食べすぎはそのもので塩分を摂り過ぎてしまいます。現代病とも言える高血圧、玄米酢をうまく利用し、バランスのとれた食生活を送りたいものです。
もっとお酢活用
切った野菜や果物が変色してしまう・・・そんなことを解決できるお酢の力をご紹介!!
レンコンにはカテキン系、ゴボウには、タンニン系のポリフェノール化合物が含まれています。
ポリフェノールとは化学構造中に水酸基(OH)が2つ以上分子についている物質の総称です。体内に取り入れられた酸素の一部は、有害物質である活性酸素となって組織細胞や遺伝子に作用し、動脈硬化や高コレステロールなどの様々な疾病の原因となりますが、ポリフェノールの抗酸化作用は、自らが酸化されることにより、これらの疾病の発生を防ぐ効果があります。
ところで、ポリフェノール類を含む組織には、これを酸化する酵素(ポリフェノールオキシターゼ)も含まれ、野菜や果物の皮をむいたり、すりおろしたりして組織を傷つけると、空気に触れて両者が反応し、メラニンという褐色の物質が生成されます。このような現象を一般 に、「褐変(かっぺん)」と呼んでいます。レンコンやゴボウが、切ったまま空気にさらしておくと、変色するのはこのような理由からなのです。
また、このポリフェノール類は苦みや渋みの原因となるアクの原因物質でもあります。
それでは、この褐変を防ぎ、かつアクを上手に抜いて、美しくおいしい料理を仕上げるには、どうすればよいのでしょうか?
まず、褐変を防ぐには、水につけこむことにより、空気に触れさせなければいいといえます。さらに、この酸化酵素ポリフェノールオキシターゼの働きを阻害することによって、酸化反応が進まないようにすればよいわけです。ここで、酢がその役割を果たします。酢に含まれる酢酸分子(CH3COOH)には、この酸化酵素の働きを阻害する効能があるからです。このような理由から、レンコンやゴボウを切った時には、いったん酢水に取るというステップを踏むことによって、見た目よし、苦みや渋みの残らないおいしい料理を作ることができるのです。なお、酢にはこれだけではなく以下のような様々な効能があります。
●カルシウム吸収(素材に含まれるカルシウムを引き出します)
●防腐・静菌効果
●食欲増進(酸味が摂食中枢に作用します)
●疲労回復(糖分と酢を同時に摂取するとグリコーゲンの再補充を促進します)
酢には上記以外にも様々な効能があります。お料理に積極的に活用して健康的な食生活をおくってみませんか?