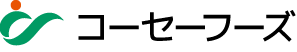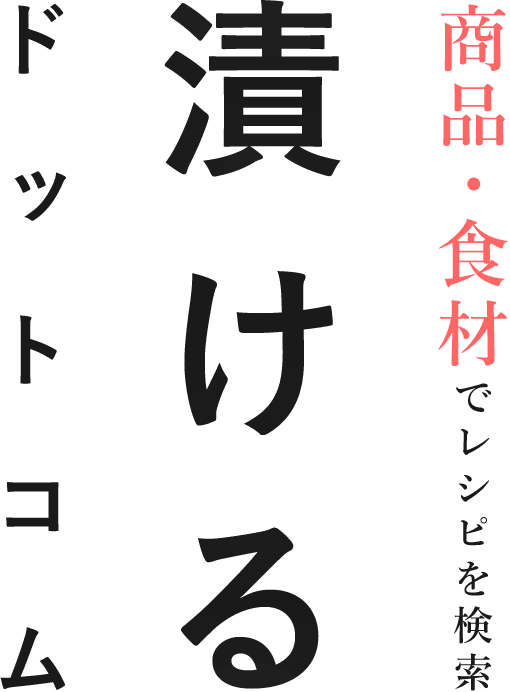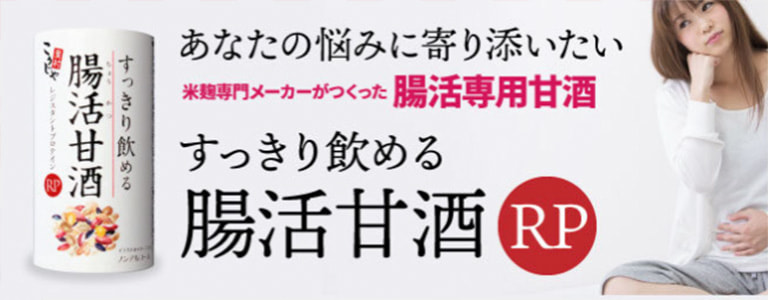梅についてのあれこれ
梅とは・・・
中国江南地方の原産。温暖で湿度の高い気候に適し、日本には古墳時代に入ってきました。
日本を代表する植物で、日本人の生活文化に深く根ざしてきました。花をめで、香りを楽しみ、その実が薬や食品として役立つ極めて有益な植物です。平安時代には梅を「むめ」と詠むこともありましたが、これは、「うめ」の響きをよりやわらかくしたものです。
落葉の小高木で葉は卵円形、有柄で互生し、花は早春、葉の先に白または紅色の五弁花を咲かせ、佳香を放ちます。梅雨時に球形果実が熟し、橙黄色になり、果肉には強い酸味があります。
成分と薬効
疲労回復から若返りホルモンまで含む有益果実
クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、ピクリン酸などの有機酸に加え、カリウム、カルシウム、リンなどのミネラルと、カロテン、ビタミンB1、B2、C、Eを含んでいます。
クエン酸は疲労物質である乳酸の生成を抑え老廃物を体内に残さないはたらきがあり、疲労の回復、肩こりや筋肉痛の防止、神経疲労の予防、肝臓病の改善に有効です。さらに、カルシウムなど水に溶けにくく吸収率の低いミネラル成分を水溶性に変え、吸収率をアップさせるはたらき(キレート作用)もあります。
ピクリン酸は肝機能を活性化させ、血管の老化を防ぎ、ウィルスやがん細胞を取り込んで消化するマクロファージを活性化させるといわれています。
また、梅干を見ると思わず唾液が出ますが、最近、この唾液の中に消化酵素であるアミラーゼ、若返りのホルモンであるパロチンが大量に含まれることがわかっており、唾液の分泌を盛んにさせることによってこれらの効果を引き出しているそうです。
梅の基本的な効能としては、ブドウ球菌や、真菌に対する強い抗菌性が知られています。胃腸の機能低下と昴進の両面を調整し、とくに慢性の下痢、胸焼け、食欲不振に有効に働きます。また、近年大きな社会問題になったO-157による食中毒は記憶に新しいところですが、梅のpHは梅干で2.0、梅肉エキスでは1.4と、O-157斤が耐えられる酸度pH2.5を大きく上まっています。昔から「梅は、三毒(食物の毒・水の毒・血の毒)を断ち、その日の難を逃れる」といわれてきたゆえんでもあります。
青梅には軽い中毒症状を起こす青酸配多糖体が含まれています。特に種子の仁に多く、「梅を食うとも核食うな」という言い伝えは科学的にも根拠がることがわかっています。
青梅を40℃で7日間焙乾し、さらに黒くなるまでふたをかぶせて加温し、黒褐色にしたものを和漢薬では烏梅(うばい)といいます。梅の強い抗菌力と整腸作用は、駆虫、慢性の下痢、急性の腹痛、嘔吐などに効果があるとされています。また、のどの渇き、咳にも有効です。
性・味
温性で酸っぱく、無毒。
クエン酸サイクル
体内の中で食べ物はぶどう糖に変わり、さらに、酵素とビタミン(主にビタミンB群)、酢によって燃焼(酸化)されエネルギーになります。このエネルギーの燃焼過程に作用する酢はクエン酸をはじめとした8種類に変化し、再びクエン酸に戻るというクエン酸サイクルを形成しています。クエン酸サイクルは、体液を弱アルカリ性に保ち、老廃物体内に残さないための大切な機能です。
このサイクルを順調に機能させるためには、必須栄養素、とくにビタミンB群の摂取を心掛け、その上でクエン酸を補給することが大切です(北日本新聞社 薬になって役立つ野菜 参照)
クエン酸について
体梅の主成分であるクエン酸は、体内で様々な活躍をします。そんなクエン酸の活躍を簡単に紹介します。
★ その1 疲労回復と老化防止!!!
体内のエネルギー代謝がうまくいかないと、栄養素の不完全燃焼から、疲れ・肩こりや、細胞の老化、動脈硬化などの成人病などの原因となる乳酸という毒素が発生します。クエン酸はこのエネルギー代謝をスムーズにして、体内の乳酸を燃焼させ、老廃物がたまるのを防ぐのです。その結果、疲れが取れ、老化の予防になるのです。
★ その2 便秘を解消!!!
クエン酸は、その酸味によって食欲を増進させ、唾液や胃液その他の消化酵素の分泌を高め、消化吸収を助け、さらに胃腸のぜん動運動を活発にして便通をよくします。
★ その3 カルシウム不足のお助けマン!!!
日本の土壌には、もともとカルシウムが少ないため、伝統的に日本人はカルシウム不足といわれています。また、カルシウムは摂取しても吸収効果が悪いので体になかなか定着しません。しかし、クエン酸がカルシウムと結びつくと、カルシウムの吸収率が良くなり、カルシウムが骨から持ち出されるのを防ぐと言われています。梅を毎日食べると、体内でのカルシウム定着率が高まるのです。
梅の成分
主成分であるクエン酸は、持ち味の爽やかさで、食欲を増進させるのみでなく、その酸味によって唾液や胃液その他の消化酵素の分泌を高め消化吸収を助け、更に胃腸のぜん動運動を活発にして便通をよくします。
血液のアルカリ度を保つミネラル
私たちの体は酸性とアルカリ性のバランスが取れてこそ、健康を維持することができるわけですが、血液のアルカリ度を保つミネラルをたっぷり含んだ梅干しを一日一粒食べる事は、健康管理の上でも非常に好ましく、古人の知恵とは言え現代人にこそ是非取り入れて欲しい食習慣と言えます。
赤じその効用
赤じそは中国中南部が原産といわれ、我が国には、むしろ梅より早い時期に渡ってきたようです。
しそは殺菌力が強く、防腐剤としても使われます。刺し身のツマに付け合わされるのも、この効果によるところが大きいからでしょう。
梅は古くて新しい健康食品
梅は1500年程前に烏梅として、日本に渡ってきたと言われます。烏梅とは、青梅をカラスのように真っ黒に薫製にした物です。
梅干しの酸っぱさは若返りの元
梅は奈良時代に薬用として、烏梅の形で中国から渡来し、熱さまし・咳止め・吐き気止めなどに用いられました。梅干しと言うだけで、口内が酸っぱくなる方もいらっしゃるでしょうが、嬉しいことに分泌された唾液中には、若返りのホルモンと言われるパロチンがたっぷり含まれているのです。
クエン酸が疲れを取り老化を予防
エネルギー代謝に重要な役割を演じているのが、クエン酸だと言うのです。エネルギー代謝が上手くいかないと、栄養素の不完全燃焼から、乳酸と言う毒素を発生させます。この乳酸は肩こりの原因になったり細胞の老化を始め、動脈硬化などの成人病の原因となります。クエン酸は新陳代謝をスムーズにして、体内に老廃物が溜まるのを防いでくれる事が、これではっきりしたのです。
現代人はカルシウムが足りない
日本の土壌には、もともとカルシウムが少ないために、日本人のカルシウム不足は伝統的と言われています。
カルシウムは梅に含まれるクエン酸と結びつくと、吸収率はグンと良くなります。梅を毎日食べていると、体内でカルシウムの定着率が高まると言うわけです。
便秘を防ぎ肌を美しくする働きも
梅の整腸作用は、女性にとって見逃せません。特に便秘は美容の大敵です。痩せようと思って減食する人がいますが、これも便秘になり易い。ある程度の量を食べないと、腸が運動してくれないのです。
栄養のバランスを保つためにも
「バランス良く食べましょう」「肉を食べたら三倍の野菜を食べなさい」これは血液が酸性にならないように、と言う戒めの言葉です。
ビフテキ・天ぷら・にぎり寿司・スパゲッテイ・ケーキ・お酒など美味しいと思う物はたいていが酸性食品です。アルカリ性食品はと言うと野菜、果物、海藻、こんにゃくなど、どちらかと言えば地味な食品が多いのです。だから、うっかりしていると、つい酸性に偏ってしまいます。これには賛成できかねます。
血液の酸性化は老化の始まり、疲れ易くなったり風邪を引き易くなったり、肌が汚くなったり、ロクな事はありません。そこで梅です。梅は酸っぱくてもアルカリ性食品です。しかもアルカリ度の高さは抜群です。
<メモ>
☆筍の皮に梅干しを三角に包んで、それをしゃぶりながら遊んだ事が懐かしい。
☆梅と言うと、徳川御三家との関係を見逃す事が出来ません。紀州・尾張・水戸など大きな梅林が今でもあります。
☆梅は杏や桜と同じバラ科に属する核果で、中国の四川省や、河北省の原産と言われ、その分布は東アジアに限られる。