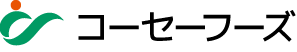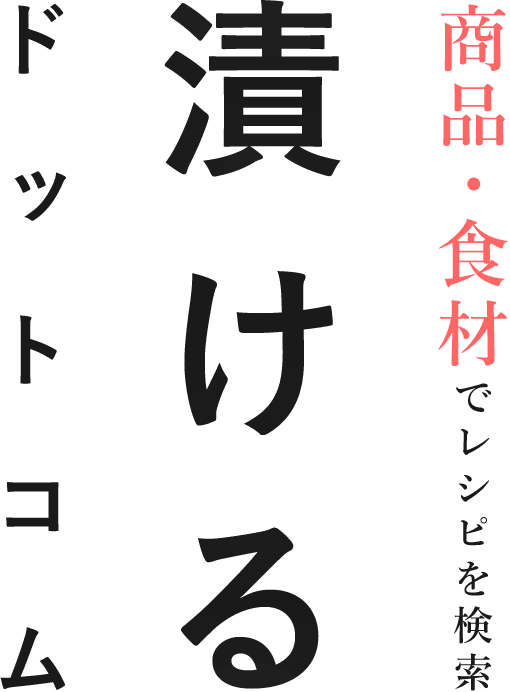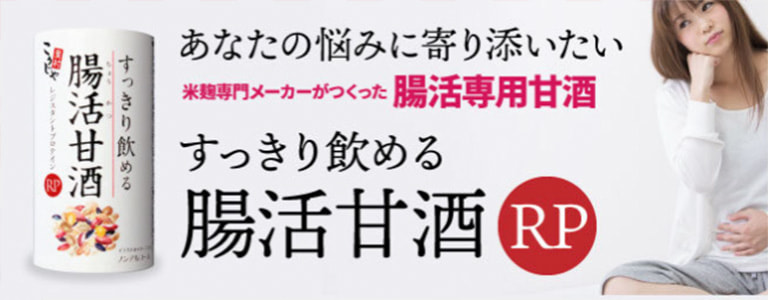ダイコンについてのあれこれ
大根とは
ヨーロッパの地中海沿岸地方が原産地といわれています。西アジアから中国、朝鮮半島を経て、日本に渡来したといわれています。古くは「おおね」とよんでいたそうです。春の七草の一つ「すずしろ」としても親しまれてきました。
数多くの品種があり、各地によって形状も異なります。例えば、鹿児島の桜島ダイコンはカブのような丸い形をしており、名古屋でよく漬物にされる守口ダイコンは世界最長のダイコンといわれ、長さは120cmにもなります。
一般的に食材として出回っているのは青首ダイコンで、広く各地に栽培されている二年草です。根生葉は、束生になり、長さ約30cmで、粗い毛があります。葉は倒披針形で、上のほうが広く、羽状に深く裂け、多数の裂片をつけます。多汁質、春に高さ1mぐらいの地上茎を出し、上部は分枝、枝先に淡紫色か白色の十字花を多数つけます。花弁は広倒卵形のくさび形で基部は長柄です。長角果で長さ4~6cm。原種はハツカダイコンです。
成分と薬効
実も葉っぱもビタミンたっぷりの重宝野菜
【根】
ビタミンCを多く含んでいます。ビタミンCは、抗酸化作用・抗菌作用があり、風邪の予防疲労回復、肌荒れの解消に効果的です。
ダイコンに含まれる成分でもっとも有名なのが、根に含まれる消化酵素ジアスターゼ(アミラーゼ)です。ジアスターゼはでんぷんを分解する酵素で、消化吸収を助け、胸やけや胃もたれを防ぎます。
また、酵素のオキシターゼが解毒作用に優れ、がん予防にも有効な成分であることがわかっています。特に、焼魚の焦げ目などに含まれるトリプP1などの発ガン性物質を無毒化するといわれています。
酵素は熱によって破壊されてしまうので、サラダなどで生でとるほうが効果的です。大根おろしにすると、20分後には80%に減ってしまいます。また、セルロースやペクチンなどの食物繊維も豊富です。そのため、便秘改善にも優れた効果が期待できます。リグニンと呼ばれる食物繊維はがん細胞の発生を抑制することもわかっています。
ダイコンおろしが辛いのはシニグリンという物質がミロシナーゼとよばれる酵素によって加水分解され、辛味の油アリルイソチアネ(からし油)になるからです。野菜ではダイコンだけに含まれ、ガンの抑制に有効なことがわかっています。アルコール抽出液は、グラム陽生菌(球菌、胞子形成桿金、コリネフォルム細菌、ストレプトマイセス菌など)や真菌に対する抗菌作用があります。この辛味成分はしっぽの部分に多く含まれ、細胞の破壊が細かいほど辛くなります。根には糖分を約3%含み、主な成分はぶどう糖、しょ糖及び果糖です。また各種の有機酸(クマール酸、カフェー酸、フェルラ酸、フェニルピルビン酸、ゲンチジン酸、ヒドロキシ安息香酸)を含みます。その他各種アミノ酸を多量に含んでいます。
薬用では、消化促進作用があり、肺を潤し、痰を除き、咳をとめ熱を下げるとされ、風邪、咳、声がれに良いとされます。生のダイコンは体を冷やして熱を下げますが、熱を加えると体を温める作用があります。成分のラファニンは食中毒を引き起こす菌が含まれるブドウ球菌の繁殖を著しく抑えます。また、水浸液(1対3)は真菌の発育を抑制します。
【葉】
ダイコンの葉はカルシウム、カロテン、ビタミンC、食物繊維を含み、小松菜やほうれん草に匹敵する緑黄色野菜です。これらビタミンやミネラルは、がんや心疾患などの生活習慣病を予防し、体の機能を維持し働きを調節して骨粗しょう症などの予防が期待できます。
特に根の部分には含まれていないカロテンは、皮膚や内臓の粘膜を強化し、ウィルスへの抵抗力を高めるはたらきがあり、胃腸を強くし、がんや骨粗しょう症、便秘の改善に有効です。購入する際には葉付きのダイコンを選び、必ず利用したい食品です。
また、ビタミンCとともに多く含まれるビタミンPは、毛細血管を柔軟に保ち、皮膚に栄養を運んで潤いを与えるとともに、ビタミンCの吸収を助けるはたらきがあります。肌荒れを体の中から改善し、美しく保ちます。
薬用では、下痢、乳腫、乳汁分泌障害、痰、咳、のどの痛みに用いられます。
干した歯を布袋に入れて口を縛り、風呂に入れると、体を温め、神経痛や冷え性などにも効果があるといわれています。
【切干ダイコン】
ダイコンの根を細切りにして天日干しした保存食です。干すことによって旨味と風味が増し、ビタミンC以外は栄養価も増します。また、生のダイコンは体を冷やすので、冷え性の人には向きません。このような場合は切干ダイコンを使った煮物や料理にすると、胃腸を温め、消化・吸収能力が高まります。
カリウム、カルシウム、ビタミンB群が、高血圧、骨粗しょう症を予防し、疲労回復にはたらき、たっぷりの食物繊維が便秘改善にはたらきます。
【カイワレダイコン】
ダイコンの若い双葉です。鉄、マグネシウム、亜鉛などのミネラルや、C、E、Kなどのビタミンがバランスよく、しかも体内に吸収されやすいかたちで含まれています。ビタミンEは、過酸化脂質の生成を抑制し、動脈硬化などの生活習慣病を予防します。
【葉ダイコン】
水栽培されたものが多く出回っています。ミネラル、ビタミンがバランスよく含まれているのが特徴で、とくに鉄、カリウム、マグネシウム、亜鉛、ビタミンC、EKなどが豊富に含まれています。ビタミンKは、カルシウムの代謝を活発にし、骨粗しょう症の予防や改善に有効です。
性・味
生は涼性で甘辛い。煮たものは温性で甘辛く、無毒。
(北日本新聞社 薬になって役立つ野菜 参照)
大根の民間療法
「大根好きの医者要らず」ということわざがあるように、大根は昔から、日常の生活の中で薬としてもさまざまに用いられてきました。
大根には各種消化酵素、ビタミンCが含まれ、健胃・食中毒に効果を発揮します。また鉄とマグネシウムを含むので粘膜の病変を癒す作用があります。
風邪・のどの痛みに→はち蜜入りおろし汁
グラス1杯の大根のおろし汁にはち蜜大さじ1をくわえて混ぜる。大根おろしのビタミンCがのどの炎症を抑えます。
風邪・熱冷ましに→大根おろし
うつぶせに寝て、大根おろしを土踏まずに載せ、ラップで覆い一晩そのまま。大根の成分が解熱効果を発揮して熱か下がります。
鼻づまりに→おろし汁
大根のおろし汁を脱脂綿に浸し鼻に詰めます。ちょっと異様ですが、大根の成分が鼻の粘膜の炎症を和らげます。
食欲不振・消化不良に→おろし汁
大根のおろし汁を30cc朝晩2回、食欲不振の方は食膳に、消化不良の方は食後に飲みます。大根に含まれる酵素が胃に作用して症状が改善されます。
便秘に→大根おろし
大根おろしを汁ごと食べます。食物繊維が腸の活動を活発にします。この食物繊維は水溶性なので汁ごと食べるようにしましょう。
急性の肩こりに→おろしシップ
大根おろしに小麦粉を加え耳たぶ程の片に練り、これをガーゼに伸ばして肩に貼ります。大根おろしの解熱作用と筋肉の消炎作用で肩のこりをほぐします。
※慢性の肩こりは温める必要があるので逆効果です。
口内炎に→おろし汁うがい
大根おろしの汁を口に含みうがいします。大根の辛味成分に含まれる硫黄化合物は抗菌効果があリ、炎症を抑えます。
大根をおいしく干すには
ポイント1:さむくなってから干しましょう
大根を霜が降りる前の暖かい時期に干すと、乾燥するよりも先にかびたり、腐ったりしてしまいます。
ポイント2:芯葉を取り除きましょう
大根を干すときに芯葉を取る理由は、大根をより美味しく干しあげるためです。
大根の美味しさとは、大根の中に蓄えられた栄養素です。
芯葉は大根の葉の中心部分からこれから大きくなろうとしている葉っぱのことです。この新しい葉っぱは他の葉に比べて、大きく育とうとするため、大根の栄養分をどんどん葉の成長に使ってしまいます。この芯葉を取ることにより、大根の成長を止め、大根の栄養成分を損なわせず美味しいまま干すことができます。
芯葉だけでなく、その他の葉っぱも栄養分は吸い取りますが、芯葉は特にたくさんの栄養分を使ってしまうので、長時間干す際少しで大根の美味しさを損なわないように、芯葉を取ることをお薦めしています。大きな外葉はそのままにして干し、大根を漬け込む際すき間を埋めたり、一番上に被せたりするのに使います。